二酸化炭素地球温暖化説は、主に炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の排出によって大気中の二酸化炭素濃度が上昇することを前提としている。これは一見当然のことのように思われるが、既に議論したピナツボ山の噴火前後の観測データに示されるように、それほど単純な問題ではない。「ミッシング・シンク」は未だに解明されてはいない問題である。
4-1 炭素循環図
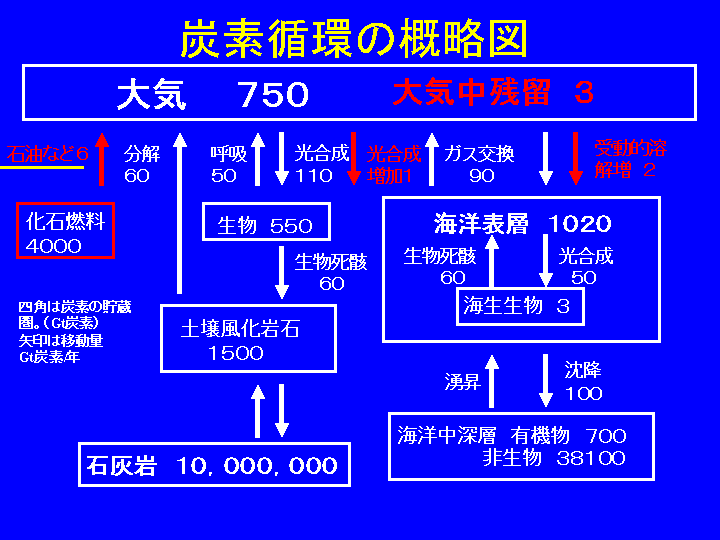
出典/ホームページ「はれほれワールド」より
まずはじめに標準的な炭素循環図を示す。図中に白の矢印で示された炭素の移動量は、炭化水素燃料の燃焼による二酸化炭素を除いた炭素の移動量を示す。赤い矢印は炭化水素燃料の燃焼によって人為的に付加された炭素の移動を示している。ただし、一旦大気中に排出された後の炭化水素燃料起源の二酸化炭素が炭素循環の中でどのように振舞うかは、今のところ明確ではない。ここに示した炭素循環図は、地球システムにおける炭素の概略の賦存量と移動量を示したものであって、その信頼性は必ずしも高いものではないし、地球システムの動的な変化によって変わりうるものである。
まず注目すべきは、炭化水素燃料の燃焼によって大気に付加される二酸化炭素による炭素の供給量は6Gt程度であって、年間に大気と生態系・海洋表層水と交換される二酸化炭素による炭素量200Gtのわずか3%に過ぎないことである。炭素循環システムには大きなリザーバー(貯蔵圏)があり、炭素の移動量も非常に大きいため、炭素循環システムの状態に何らかの変化がおきて、平衡状態が少しでも変われば図に示した値は容易に変わりうることを考えなければならない。果たして近年観測されている大気中の二酸化炭素濃度の変動が炭化水素燃料の燃焼に伴って人為的に付加された二酸化炭素によるものかどうかを特定することは、それほど容易なことではない。
例えば前セクションで検討したピナツボ山噴火の事例からも、海洋表層水の温度効果による二酸化炭素の吸収特性の変化は小さくない。次に示す図は、二酸化炭素の溶解度の温度効果を示している。

縦軸は、1気圧の二酸化炭素が水1リットルに溶解する量(モル)を示している。水温の上昇によって溶解量は顕著な変化を見せる。例えば単純に計算すると、海洋表層水の温度が 20℃とした場合、1℃の温度上昇によって二酸化炭素の溶解量は2%程度減少することになるであろう。炭素循環図によると、海洋表層水に含まれる炭素量は 1020Gtであるから、この温度効果だけで大気中に余分に放出される二酸化炭素による炭素移動量は実に20.4Gtになる。
次に示す図は、この100年余りの海面水温の変動を観測した図である(このセクションのテーマではないが、太陽黒点数と平均海面水温の変動は良く似た傾向を示していることにも注目いただきたい)。

観測値によると、1910年から1980年の平均海面水温の上昇は0.5℃程度である。これを単純に当てはめると、この間温度効果だけで10Gt以上の炭素が余分に大気中に放出されるようになったはずである。余分に排出された二酸化炭素はどこに消えてしまったのであろうか?
実際の炭素循環の変化はこれほど単純なものとは考えられないが、少なくとも炭素循環システムのさまざまな変動要因を詳細に検討しない限り、単純に人為的に放出された二酸化炭素の半量が大気中に残留して大気中の二酸化炭素濃度が上昇するというのは非科学的な主張である。
4-2 海洋工学の成果から
前節で行った試算は、極めて粗雑なものに過ぎないが、現在、二酸化炭素地球温暖化説で主張されている炭素循環も、多様な様相を見せる実際の海洋の状態を観測した結果に基づくものではなく、単純なモデル計算によって海洋の二酸化炭素吸収量を算定したものであり、とても実態を反映しているものとはいえない。ここでは、角皆静男氏の観測に基づく実証的な海洋工学の研究成果を紹介する。
(1) 「Littera Populi 2号1999年」アカデミア・ポプリより全文引用
海洋が吸収する二酸化炭素
角 皆 静 男
昨年の京都会議で、世界先進各国は、初めて二酸化炭素の放出量削減を決めましたが、これで安心できるでしょうか。私どもの研究からこの点を考えてみます。
1.今年の夏の高温と地球の温暖化
今年は、たいへん暑い夏でしたが、ついに360ppmを越えた大気の二酸化炭素による地球温暖化のせいだったのでしょうか。これが、二酸化炭素による直接的温室効果でなかったことは確かです。ただ、その効果が玉突きの玉のように複雑な地球系の中で増幅され、間接的に暖めた可能性は否定できません。それは、過去の地球での出来事から言えます。
2.過去の地球で起こったこと
ここ百万年の地球では、氷期と間氷期が周期的に激しく繰り返され、ヨーロッパでは、平均気温で6~10度変動しました。これは東京と北海道の気温差に相当します。この時、二酸化炭素も同様に変動し、氷期に180ppm、間氷期に280ppmでした。ですから、二酸化炭素が関係していたことは確かですが、その直接的温室効果だけでは、この気温変動にはなりません。また、その引き金は、ミランコヴィッチ周期といわれる地球の軌道要素が十万年、四万年、二万年の周期で変動し、日射の季節変化緯度変化が変わることでした。それを地球システムが気候変動に拡大しました。さらに、これ以外に、短周期の変動もあります。
3.気候変化に関する政府間パネル
国連傘下の政府間機関は、気候変化に関する政府間パネルをつくり、科学者に地球の将来を予測させました。その報告書には、このまま放っておくと、21世紀末には、大気中二酸化炭素は700ppmに近づき、その直接的効果だけで、平均気温は2度(札幌が盛岡になる)、海面は50㎝近く上昇するとあります。しかし、地球システムが変わることで変わる効果は考慮せず、今まで通りの海を前提にしています。私どもとは、その「今の海」の認識も違っています。
4.海洋が吸収する二酸化炭素量
この報告書では、人間活動による年間放出量、71億トンの炭素のうち、モデル計算で得た海洋の吸収量の20億トンを信頼し、大気に残る32億トンを除いた残りの19億トンを陸の生態系に入るものとしました。海洋の吸収量の実測値はありませんが、大気と海洋間の濃度差(分圧差)に交換の速さを掛けて交換量を出し、世界の海について足し合わせ、この程度の値になるという報告はあります。しかし、このやり方で正確な値を得ることは不可能です。私どもは、変化量が微弱で正確な測定は必要ですが、西部北太平洋で、この18年間の海水中全炭酸の増加量を実測し、この海では、全世界の海洋面積あたり年間36億トンの吸収になると報告しました。太平洋が二酸化炭素を吸収しやすい海であるにしても、世界の海の半分以上を占める太平洋を欧米の研究者が軽視したことが、認識にずれを生じさせた原因と考えています。
5.二酸化炭素吸収力の大きい太平洋水
深層水は、北大西洋で潜り込み、南下し、南極海から北上し、北太平洋で浮上するのは二千年後です。南極海では、一部が浮上し、酸素を補給し、二酸化炭素を放出し、冬のため、リン酸や硝酸などは生物による光合成に使われずに、また潜ります。太平洋で浮上すると、リン酸や硝酸は完全に使われますので、二酸化炭素は南極海で放出した分だけ余分に溶け込めます。また、海底などで溶けた炭酸塩の分だけ二酸化炭素を溶かしやすくしています。さらに、この水が潜り込んでから大気中濃度が増加した分だけ溶けやすくなります。これらは合計、年間10億トンになります。つまり、太平洋水は、大西洋水よりそれだけ余分に吸収できます。この大きな吸収能力と、実際にその吸収を起こす次の四過程をモデル計算者達が、見落としたり、過小評価しているというのが私どもの主張です。
6.二酸化炭素の吸収過程
その4過程としては、第1に南極海や北太平洋でできる中層水があります。中層水は、水深1,000m程度までで、量は深層水の10分の1程度ですが、寿命が10分の1以下なので、ここに入る二酸化炭素は深層水以上に大きいことになります。第2に、私が名付けた大陸棚ポンプです。
これは大陸棚で冷やされて底に沈んだ水が10億トン程度の炭素を大気から吸収して外洋に送り出しています。モデル計算ではこれを無視しています。第3は、気体交換に果たす荒天とその時に巻き込まれる泡の効果の過小評価です。さらに、泡の効果により二酸化炭素の交換速度は、難溶性の気体より大きくなります。第4に、溶存ケイ酸の役割です。海洋の生物が有機物をつくると、大気の二酸化炭素を吸収しますが、炭酸塩の殻をつくると、逆に放出します。この量比は、溶存ケイ酸の多い西部北太平洋や南極海では大きく、東部太平洋や大西洋で小さいのです。欧米の研究者は、主に溶存ケイ酸の少ない海で研究しています。
7.変化する海洋
海洋の吸収量がどう変わるかによって大気中の二酸化炭素濃度はたちまち変化します。現在や過去の地球での出来事をもとに、その仕組みを解く必要がありますが、現状はこの程度で、まだまだ研究不足です。したがって、冒頭の放出量の削減は、しないよりはした方がよいでしょうが、したからといって、今後何が起こるかわからないとしかいえません。
(2) (97.9.23-25)資源・素材 '97 資料、資源と環境(1997.9.23-25), 48-51(1997)より抜粋
角皆氏のホームページには、このほかにも膨大な著作が公開されているので、興味のある方はご覧いただきたい。
炭素など化学物質の生物地球化学的循環
北大・大学院・地球環境 角皆 静男
1.問題のありか
人間活動によって大気中の二酸化炭素など温室効果気体の濃度が変わり、地球が温暖化し、地球環境が変化することが心配されている。一方で、大気中の二酸化炭素濃度が多少増えたとしても、地球が温暖化することはないという研究者もいる。この問題を複雑にしているのは、地球が複雑だからであるが、問題点を少し整理してみよう。
1) 大気中の二酸化炭素濃度が増大すれば、その温室効果(赤外線吸収効果)が増大することは、物理化学的な事実であり、確かなことである。
2) 大気中の二酸化炭素など温室効果気体の濃度が増大しても、それが吸収する波長帯の赤外線がなければ、気温は上昇しない。つまり、対流圏の二酸化炭素濃度が増大して対流圏の気温が上昇すると、成層圏の気温は逆に下がる。
3) 太陽から直接地表に届く光(地表が吸収する短波)が減れば、地表から放出される赤外線も減る。つまり、太陽光の反射率(アルベド)が増大すれば(例えば、雲の増大、エーロゾルの増大などにより)、気温は下がる方向に変化する。
4) 少量のフロンなどに比べ、多量に存在する二酸化炭素の方が一分子あたりの温室効果が小さいのは、分子吸光係数が異なるだけでなく、赤外線の吸収帯が異なり、すでに吸収すべき赤外線が大きく減ってしまっているからである。
5) 地表付近の大気でもっとも温室効果の大きな気体は、二酸化炭素ではなく、水蒸気である。
6) 当然のことながら、大気中に放出された温室効果気体は、そのまま大気中に留まるわけではなく、海、土、植物に取り込まれたり、光などにより分解されたりする(この尺度が平均滞留時間である)。
7) 上記の交換や変化の過程は、地球が変化することで変化し、それがまた地球を変える。つまり、地球システムにはフィードバック過程が働いている(過去の地球に働いたフィードバック過程の結果は南極の氷などに記録されている)。
8) さらに上記のフィードバック過程は、非線形(与えた効果に比例しない)であるばかりでなく、時間的にもさまざまなスケールを持っている(いつ顕れ、いつ落ち着くかわからない)。
さて、これで問題点は多少整理されたとしても、問題は拡大する一方である。先にあげた地球は温暖化するかの問いかけの前に、地球は温暖化しているかの問題がある。図1(略)をみると、少なくとも、最近、暖かな年が多いことは確かであり、温暖化が始まったようにも見える。図2(略)に示した大気中の二酸化炭素濃度は、最近になって急上昇しており、それが原因かもしれない。しかし、過去に大気中の二酸化炭素濃度がそれほど変化しなくても、急激に気温が変化した記録がある(この結果を疑問視する説もあるが)。従って、先の気温上昇は(あるいはその一部は)、自然の変動の一部が現れただけかもしれない。さらに、しかし、もしその自然の気温変動が二酸化炭素による温室効果がなければ下がっていく方だったら、現在増加している二酸化炭素の効果は、最近の暖かさ以上の暖かさをもたらす効果を持っていることになる。
2.IPCC報告書
複雑な地球システムにおいては、すべてが大きな不確かさを持つ。それで、慎重な科学者は何もいわない。逆に、何をいっても完全に否定することはきわめて難しく、かなり不確かな説でもまかり通ってしまうので、いろいろな説が登場する。どれを信用すべきか判断に困る。一方で、政策決定者は、地球環境問題に緊急に然るべき手を打たなければならない。そこで、国連の下部機関であるWMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)は、IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change、気候変化に関する政府間パネル、Changeを日本、特に物理系の研究者は変動と訳しているが、私は変化と訳したい。変動は Variationである)をつくり、慎重な科学者になんとかもっとも確からしいものを選び、地球の将来を予測するよう諮問した。その結果が1990年に第1回報告書、1995年に第2回報告書としてまとめられた。最初、この分野の科学者達は、非科学的として冷ややかであったが、自分達の将来の研究環境に関係しそうなので、真剣になってきた。
第1回報告書では、大気中二酸化炭素の収支について、まだ、行方不明の吸収源(ミッシングシンク)があると書いてあった。ところが、下表のように第2回の報告書では、これは陸の生態系が吸収していることになった。
表1 1980年代における人間活動に由来する炭素の収支 (単位はGtC/yr)
1. 化石燃料の燃焼 5.5±0.5
2. 熱帯雨林の破壊 1.6±1.0
3. 大気圏への供給=1+2 7.1±1.1
4. 大気圏に残留 3.3±0.2
5. 海洋の吸収 2.0±0.8
6. 北半球の森林再生 0.5±0.5
7. 肥沃化効果=3-(4+5+6) 1.3±1.5
上表(単位のGtC/yrは、ギガトン、1015g、単位での1年当たりの炭素の移動量をあらわす。6の北半球の森林の再生というのは、先進国では植林により森林が復活しているとするものであり、7の肥沃化効果というのは、二酸化炭素の増加、窒素酸化物の増加、気温の上昇により植物の光合成が活発になったとするものである)でもわかるように、まだ不確かさの幅はきわめて大きい。しかし、ミッシングシンクという用語が消えたのは、海洋の吸収量がかなり確実になり、海でなければ陸でしかないというのがその理由である。ところが、海の吸収量はモデル計算値であって、実測値ではない。海洋、特に西部北太平洋で観測している者にとって、どうもこの結論はしっくりこない。そこで、我々の観測値と考えを紹介しながら、この問題に迫ってみよう。
3.地球上における炭素循環と海洋
複雑な地球システムにおける炭素の振る舞いを完全に記述することはとうてい不可能であるから、まず、現在の地球上における炭素の収支表をつくってみて、注目すべき点を拾い出してみる。図3は、私が1989年につくった地球上における炭素循環の図である。この時、私は、人間活動で放出された1年当たり6ギガトンのうち、3ギガトンを海が吸収しているものとした。それで、海洋に入る炭素の量がの方が出る量より1年当たり3ギガトン多くなっているが、海から出、陸で風化に使われ、河川から入るという人間活動が活発になる前の自然のサイクルで0.6ギガトンほど移動していたので、細かくいえば、これは2.4ギガトンになる。
図3を見ると、陸も海も大気との間で年間100ギガトンもの二酸化炭素をやりとりしており、その間の2-3%の小さな差額を問題にするのであるから、きわめて難しい問題であることが理解できよう。特に、陸は、地域的(地表だけでなく、地中もある)、季節的変動(その上に昼夜の差がある)がきわめて大きく、そこでの正味の移動量(フラックス)を全地球について観測しなければならない。したがって、現時点で陸の方から決定的結論を得ることは、ほとんど不可能である。それで、海洋の方を眺めてみたい。
海洋で問題になるところは、正味の年間の変化量が2-3ギガトンであるから、フラックスがその10倍以上となる過程であろう。それは、大気海洋間の気体交換、海洋生物による光合成、中深層水の形成であろう。特に海面での気体交換は、大部分がそこを通過しており(ごく一部河川水から入る)、最も重要で、関心を集めている。その手法は、大気海洋間の濃度差(分圧差、フガシチー差、活量差)を測定し、これに交換速度を掛けて、フラックスを求めるのが主流である。しかし、2つの因子双方が場所により、時により大きく変動しており、正確にフラックスを求めることは、これもきわめて難しい。もちろん、海面で起こる現象や過程の研究に表面海水に溶けた二酸化炭素の活量を測定することは、有力な研究手段である。それで、私は海水に溶けた人間活動起源の二酸化炭素の蓄積量を測定した。この方法の欠点は、変化量が微弱なことであり、高精度な分析法と解析法(たとえば、海面から潜り込んでからの時間と濃度の関係の解析など)が必要なことである。
私が主に西部北太平洋で観測した結果から得た結論は、モデラー達は、北太平洋水の吸収しやすい特徴と後述する4つの過程を見落とすか過小評価をしたためで、これを正しく評価すれば、海洋の吸収量は年間3ギガトン程度にはなるというものである。そうなってしまったのは、欧米の研究者にとってこの海域はあまりに遠く、どうしても近くの海しか対象とならなかったためと考えている。最近、カナダのC. S. Wong博士は、極東ロシアと共同研究を行い、これまでの計算値は、北太平洋だけで年間0.9ギガトン少なかったと述べている。
私は、中深層水が浮上したときの二酸化炭素の吸収のしやすさについて、Potential Sink Capacityを定義した。一般に浮上した水は、中深層にあったとき、上から降ってくる有機物粒子を分解して再生した炭酸によって、また水温が上がって、大気に二酸化炭素を放出しやすい状態になっている。しかし、表面で、再生してできた栄養塩が使われてしまい、冷やされて、再び潜り込む寸前になったときには逆に吸収する。これはその量をあらわしている。この値は、通常は、現在とその水が潜り込んだときとの大気中二酸化炭素の濃度の差でしかない。しかし、北太平洋水では、その値より大きくなる。その原因は、北太平洋深層水は、北大西洋で潜り込んで生まれ、南下して南極海に入ったとき、一部が浮上することにある。南下中に再生した炭酸はこの時一部が失われる(溶存酸素は逆に供給される)が、栄養塩の方は冬のため、失われずにまた潜り、北太平洋に運ばれる。このPotential Sink Capacityが大きい水が湧昇すればするだけ、大気の二酸化炭素が溶け込むことになるが、それには時間がかかる。それで実際には次の4つの過程が関係する。
1) 中層水の形成
中層水とは、低温であるが、低塩分のため、深層までは潜れない水のことで、北太平洋と南大洋(大西洋、インド洋、太平洋を北に向かう)で形成されている。核実験による14Cやトリチウム(Tsunogai et al., 1995)、あるいはCFCs(日本ではフロンという)(Tokieda et al., 1996)を化学トレーサーとして用いると、西部北太平洋の水深1000m程度にまで中層水が広がっていることがわかる。そして、この北太平洋中層水の形成域は、西太平洋の40-45゚N付近らしいこともわかる。南大洋の南極中層水の方が少し高緯度で形成されているようである。
この中層水の平均寿命(存在量/年間形成量)は、数十年から百年程度になる。深層水の平均寿命は1000年程度なので、北太平洋水に関わる年間形成量は、中層水の方が深層水より大きいことになり、人為起源の二酸化炭素の吸収に関しては、中層水の方がより重要ということになる。なぜなら、中層水の存在量は1/10程度なのに、寿命は1/10以下だからである。この中層水の形成量(皆同じ寿命を持っているわけではないので、全北太平洋におけるトレーサーの分布が必要である)とその経年変化の正確な見積もりができれば、今後の大気中二酸化炭素濃度の変化の見積もりに算入できるであろう。
2) 大陸棚で起こる過程
大陸棚は全海洋の8%に未たず、生物生産は活発でも、有機物は比較的早く分解してしまうので、二酸化炭素の吸収に関してはこれまで注目されてこなかった。しかし、よく知られているように、海流は熱を低緯度から高緯度に運び、この熱を放出して、穏やかな地球を造っている。いいかえれば、高緯度に行くほど海水温は下がり、その程度は、同じ緯度なら浅い海の方が大きいことになる。つまり、海面から熱が放出されている海域の同緯度では、大陸棚の方が水温が低い。水温が低いと、大気の二酸化炭素は溶けやすい。また、活発な生物活動でできた有機物粒子は、沈降して海底で分解し、炭酸塩濃度の高い水をつくる。その水が表面に現れれば、大気に戻ってしまうが、冷たい水は、同時に重いので、外洋水と等密度面混合をしたとき、下の、より深い方に入っていく。
私ども(Tsunogai et al., 1997)は、この5年東シナ海において観測を続け、上記の筋書き通りであることを確かめ、これを大気中二酸化炭素の吸収に関するContinental Shelf Pump(大陸棚ポンプ)と名付けた(大気の二酸化炭素を海洋に送り込む過程をポンプと称している。生物ポンプ、溶解ポンプ、アルカリポンプがある)。
3)高緯度海域における気体交換
大気海洋間の気体の正味の交換量は、界面での活量差と交換速度に依存する。交換速度については、現在、風速の関数として表したLiss and Merlivat(1986)の式が一般に使われている。ところが、洋上の風速分布をもとに見積もった全世界の海の平均的交換速度は、海洋における14C (天然でも、人工でも)の収支計算から求めた平均的値より小さい。我々は、西部北太平洋においてラドンの放射非平衡量(大気に出た分だけ、ラジウムより放射能が少なくなる)より交換速度を求めた。その結果、冬季に大きな低気圧が通過した後、その風速と上記の式から見積もられる値よりずっと大きな交換速度になることがわかった。これらをもとに、気体の交換は、穏やかな海ではほとんど起こらず(無視でき)、荒天下に泡(水深20m以上にも達する)の効果で一挙に起こるのではないかと推論した。荒天にさらされる割合は、冬の高緯度海域で大きく、その効果は、酸素よりも、交換平衡に時間のかかる二酸化炭素で大きい。
4) 溶存ケイ酸の役割
大西洋深層水に比べ、太平洋深層水は約7倍のケイ酸を含むが、硝酸やリン酸は2倍程度でしかない。従って、この深層水が湧昇するベーリング海やオホーツク海を含む北部北太平洋では、北大西洋に比べ、絶対量においても相対比においても、けい藻がより多く繁殖する (Tsunogai and Watanabe, 1983)。Tsunogai and Noriki (1991)は、北西部北太平洋で有機炭素の沈降粒子束が極めて大きいばかりでなく、有機態炭素/炭酸塩態炭素の比も大きく、有機炭素の深さによる減少率は逆に小さい(沈降粒子が大きいので)ことを見つけた。すなわち、ここで、いわゆる生物ポンプがよく働いているということである。中層水が湧昇している東部や赤道太平洋では、炭酸塩の割合が大きい。
炭酸塩粒子の形成は、海水の溶存二酸化炭素の活量を高めるので、単に生物生産量の絶対値に注目するのではなく、その質、つまり、有機態炭素/炭酸塩態炭素比に注目しなければならない。この点で、北西部北太平洋と太平洋深層水の湧昇の消長は極めて重要である。
4.フィードバック過程とこれからの地球
ミッシングシンクの問題は、その解答を我々が知らないだけであり、それが明らかになってもこれからの地球がどうなるかの解答にはならない(その第1歩として有力な手がかりにはなる)。これのためには、現在の地球がどう変わりつつあるかつかみ、そこに働くフィードバック過程を明らかにしなければならない。これに関連して次のことを述べておきたい。
1) 大気中二酸化炭素の溶解度の変化 水温が上昇すると、二酸化炭素は溶けにくくなる。溶解度は、水温が1゚C上昇すると約4%減少する(溶解ポンプ)。この100年に東部北太平洋で、水温が1゚C上昇したという報告もある。大気中二酸化炭素の濃度上昇で海洋への溶解量も増えるはずであるが、これによって、その10年分が帳消しになったともいえる。今後、表面水温が上昇すれば、ますます溶けにくくなる。
2) 中深層水の形成量の変化 深層水は、冬季冷やされ、低温の重い水をつくる。結氷しても重い高塩分水ができる。こうして、沈み込む。また、強い成層化は湧昇にも影響を与える。水温上昇は、中深層水の形成量を減らすことにつながるだろう。さらに、深層循環にも影響を与える(例えば、逆に太平洋から大西洋に流れる)かもしれない。
3) 生物生産量の変化 中深層水の形成量が減れば、それだけ湧昇する水の量が減ることになる。そして、その分だけ下から補給される栄養塩が減り、生物生産量は減る。しかも、太平洋深層水の湧昇量が減れば、ケイ素の量が大きく減るから、炭酸塩殻を持つ生物の割合が増え、ますます生物による二酸化炭素の吸収力(生物ポンプ)は小さくなる。
現在の海洋による大気中二酸化炭素の吸収に関するモデル計算ではこれらのことがまったく考慮されておらず、またその他にもっと重要なフィードバック過程があるかもしれない。過去の地球から、現在の地球から、まだまだ多くのことを学ばなければ、当初の設問に対する解答は出てこない。
角皆氏のレポートからは、極めて複雑な海洋システムの機構を垣間見ることが出来る。IPCCをはじめとする二酸化炭素地球温暖化説を主張する研究者は、自然に対してもっと謙虚になる必要があると考える。二酸化炭素の大気中濃度の変動機構だけに限っても、その変動要因は温度効果だけにとどまらず、深層水の物理・化学的な変化、海洋表層水と中・深層水との物質交換、大陸棚における生物化学的な影響、海洋表層の波の運動エネルギーによる吸収特性の変化など、考えるだけでも多岐にわたる。角皆氏が述べているように、更に現在想定されていないようなフィードバック機構の存在も否定できない。また、たとえこれが明らかになったとしても将来的に炭素循環システムがどのように変容するのかは、また別の問題なのである。
現段階において、大気中二酸化炭素濃度の上昇が人為的に付加された炭化水素燃料の燃焼を起源とする二酸化炭素であるという主張はほとんど科学的な根拠がないよう思われる。
関連レポート
人為的二酸化炭素地球温暖化仮説を否定する 近藤邦明 (HP管理者)
大気中に含まれる人為起源二酸化炭素量の推計 近藤邦明 (HP管理者)
二酸化炭素温暖化仮説とエントロピー 近藤邦明 (HP管理者)New!
「CO2地球温暖化説は科学ではない」(2006.7.28) 近藤邦明より一部抜粋
二酸化炭素地球温暖化脅威説批判 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より
新規作成:Mar.19,2008
最終更新日:Mar.13,2009